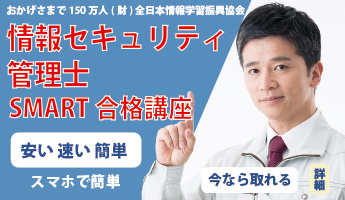【サイバー攻撃対策】企業が今すぐ実践すべきサイバーセキュリティ5選!
2025.4.10
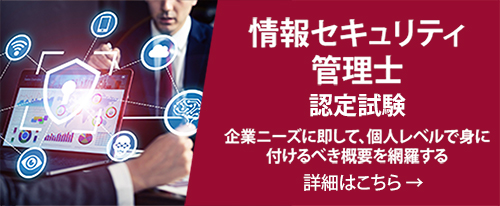
リスクマネジメントを学ぶ情報セキュリティ管理士
【サイバー攻撃対策】企業が今すぐ実践すべきサイバーセキュリティ5選!
企業の重要な経営課題のひとつが、サイバー攻撃から会社を守るためのサイバーセキュリティです。しかし、サイバーセキュリティの具体的な方法がよくわからない、という方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、サイバーセキュリティとは何かをわかりやすく解説するとともに、サイバー攻撃の主な種類、代表的なサイバーセキュリティの対策を紹介します。この記事を読むことで、どのような対策を講じるべきかが理解できるでしょう。
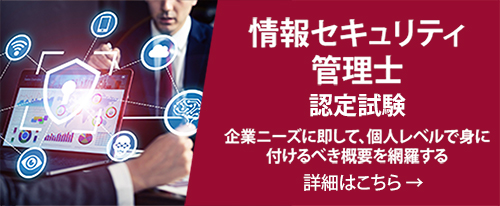
リスクマネジメントを学ぶ情報セキュリティ管理士
サイバーセキュリティとは?

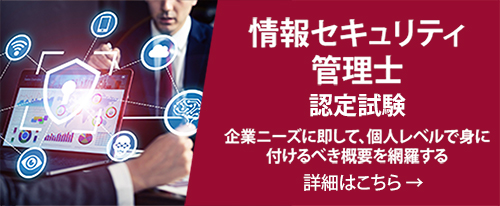
リスクマネジメントを学ぶ情報セキュリティ管理士
サイバーセキュリティとは、コンピューターシステムやネットワーク、データといった情報資産を、サイバー攻撃から守る対策です。サイバー攻撃とは、ネットワークを介して個人や企業のコンピューターやサーバに侵入し、データの改ざんや情報の漏洩、不正アクセスを行うことです。
サイバー攻撃の被害に遭うと顧客情報の流出や事業の停止、損害賠償請求などさまざまなリスクを伴います。このようなリスクを軽減し、日々安全に業務を行うためにも、サイバーセキュリティは企業にとって必要不可欠な対策です。
サイバー攻撃にはどのような種類があるのか

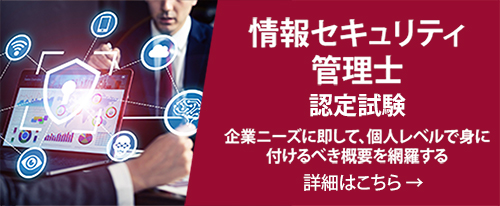
リスクマネジメントを学ぶ情報セキュリティ管理士
企業や個人に被害をもたらすサイバー攻撃には、いくつかの種類があります。それぞれ詳しく解説します。
マルウェア攻撃
サイバー攻撃の大半を占めるのが、マルウェア攻撃です。マルウェアとは、「Malicious(悪意ある)」と「Software(ソフトウェア)」の2つの単語を組み合わせた造語です。その名のとおり、悪意のある目的で作成されたソフトウェアやプログラム全般をマルウェアと呼びます。
代表的なマルウェアは、「トロイの木馬」「スパイウェア」「ワーム」「エモテット」などです。主な感染経路はメールの添付ファイルや不正サイトへのアクセスなどで、感染するとコンピューター内に保存されている情報の消失や書き換え、流出などの被害をもたらします。
フィッシング詐欺
実在する企業や団体、組織になりすましたメールやSMSを送りつけます。貼り付けたリンクをクリックさせて偽のWEBサイトに誘導し、クレジットカードなどの重要情報を盗み出す手口です。
フィッシングの綴りは「phishing」で、「fishing(魚釣り)」と「sophisticated(洗練された)」というふたつの単語を組み合わせた造語だといわれています。近年は個人だけでなく、企業を狙ったフィッシング詐欺(BEC)も増加しています。
企業がフィッシング詐欺に遭うと機密情報や顧客リストが流出し、社会的信用を失いかねません。また、最近は手口も巧妙化しており、ひと目で詐欺だと判別できないケースも少なくありません。
コンピューターウィルス
不正プログラムの一種で、感染するとファイルが破壊されたりおかしなメッセージが画面に表示されたりといったさまざまな症状が発症し、大きな被害をもたらします。一般的には、以下の3つうち1つ以上の機能を有するものが、コンピューターウイルスと定義づけられています。
1.自己伝染機能
自らをコピーして自己増殖を繰り返し、他のシステムにも伝染する機能
2.潜伏機能
特定の処理回数や時間など、一定の条件を満たすと発症する機能
3.発病機能
ステムやデータを破壊するなどコンピューターに異常動作をさせる機能
コンピューターウイルスは、主にメールやネットワーク経由および外部の記憶媒体を通じて感染するのが特徴です。
DoS攻撃・DDoS攻撃
DoS攻撃は「Denial of Service Attack」の略で、サーバに大量のデータを送り付け、WEBサイトをパンクさせる攻撃です。一方DDoS攻撃は、「Distributed Denial of Service attack」の略で、複数のIPを利用して、DoS攻撃を仕掛ける手法を指します。
DDoS攻撃では、攻撃者がマルウェアなどで乗っ取った複数のコンピューターのIPを不正に利用し、DoS攻撃を行うのが特徴です。DoS攻撃はWEB事前に同一IPからのアクセスを回数制限しておけば容易に防げますが、DDoS攻撃は対処しきれないほど大量のIPから攻撃されるため、防ぐのが困難です。そのため、DoS攻撃よりもDDoS攻撃のほうが厄介だといわれています。
ランサムウェア
マルウェアの一種で、「Ransom(身代金)」と「Software(ソフトウェア)」の2つの単語を組み合わせた造語です。その名のとおり、ファイルを暗号化するなどして利用不可能な状態にして、そのファイルを元に戻すことと引き換えに身代金を要求する攻撃です。
ランサムウェアの攻撃方法として、主に以下の2つが挙げられます。
- ・ノーウェアランサム攻撃
データを暗号化することなく盗み出し、公表しない代わりに身代金を要求する手口
- ・ダブルエクストーション
データを暗号化したうえで盗み出し、データの複合および公表の2つの脅迫を行う手口
これまでは、不特定多数の企業や組織にメールを送ってランサムウェアに感染させる「ばらまき型ランサムウェア」が主流でした。しかし近年では、特定の企業や組織に狙いを定めて攻撃する「標的型ランサムウェア」が主流になっています。
サイバーセキュリティの必要性
はじめにお伝えしたとおり、サイバーセキュリティとは大切な情報資産をサイバー攻撃から守る対策で、企業が安全に業務を遂行するための必須課題です。 2023年には、過去3年の日本国内におけるサイバー攻撃による法人組織の累計被害額が、1億円を超えました。サイバー攻撃は年を追うごとに手口が巧妙になっているため、被害額は今後さらなる増加が考えられます。
そのため、個人情報や顧客情報など、重要な情報を取り扱う企業や組織は、ますますサイバー攻撃のリスクにさらされることになるといえます。巧妙なサイバー攻撃を回避し、リスクを最小限に抑えるためにも、サイバーセキュリティは企業にとって重要な経営課題のひとつです。
代表的なサイバーセキュリティ5つ
はじめにお伝えしたとおり、サイバーセキュリティとは大切な情報資産をサイバー攻撃から守る対策で、企業が安全に業務を遂行するための必須課題です。 2023年には、過去3年の日本国内におけるサイバー攻撃による法人組織の累計被害額が、1億円を超えました。サイバー攻撃は年を追うごとに手口が巧妙になっているため、被害額は今後さらなる増加が考えられます。
そのため、個人情報や顧客情報など、重要な情報を取り扱う企業や組織は、ますますサイバー攻撃のリスクにさらされることになるといえます。巧妙なサイバー攻撃を回避し、リスクを最小限に抑えるためにも、サイバーセキュリティは企業にとって重要な経営課題のひとつです。
メールセキュリティの強化
メールセキュリティとは、メールアカウントおよび通信を不正なアクセスや侵害から守る対策です。おもにビジネスメール詐欺やフィッシング詐欺、標的型攻撃メールといったサイバー攻撃対策に有効です。メールセキュリティの主な機能は、以下のとおりです。
- ・アンチウイルス機能
メールの添付ファイルやリンクに潜むマルウェアを検出・排除する機能
- ・本文および添付ファイルの暗号化機能
メールの内容や添付ファイルを暗号化し、情報の機密性を保持する機能
- ・スパムフィルタリング
受信トレイに届くスパムメールを検出・ブロックする機能
- ・認証機能
なりすましメールかどうかを確認する機能
- ・誤送信防止機能
送信前に送信先や添付ファイルをチェックし、誤った宛先への送信を防ぐ機能
- ・データ損失防止機能
メールに含まれている重要データを監視し、セキュリティポリシーに基づいてフィルタリングする機能
- ・ログ監視機能
メールの送受信に関するログを収集して、誤送信や不審なメールのやり取りを監視する機能
メールセキュリティを強化することで外部からの攻撃を防ぐだけでなく、メール経由での機密情報の持ち出しやメールの誤送信も事前に阻止できます。
パスワードのセキュリティの強化
パスワードを従業員の間で使いまわしたり、だれでも覚えやすいように簡素化したりしていると、サイバー攻撃のリスクが高くなってしまうため、セキュリティを強化する必要があります。具体的には、以下の対策が有効です。
- ・管理者を決める
従業員のなかからパスワードマネージャーを決め、アクセス権を委任する
- ・複数のアカウントで使用しない
同じパスワードを複数のアカウントで使用すると安全性が低下するため、アカウントごとのパスワードを設定する
- ・パスワードを適切に保管する
パスワードや機密情報を暗号化して保管するパスワードボールドを使用するなど、パスワードは厳重に取り扱う
- ・強力なパスワードを生成する
パスワードマネージャーなどのツールを利用して、解析されにくいパスワードを生成する
- ・多要素認証を導入する
パスワードとともに、PINコードや秘密の質問の回答などを入力する多要素認証を取り入れる
パスワードセキュリティを強化することで、情報漏洩のリスクが大幅に軽減されるでしょう。
アプリケーションセキュリティ
アプリケーションに潜んでいる脆弱性を特定・修正してサイバー攻撃のリスクを軽減させる対策を、アプリケーションセキュリティといいます。
近年アプリケーションは複雑化しているため、なかには管理が行き届いていないものもあります。そのようなアプリを使用して業務を行うと、サイバー攻撃のターゲットとなるリスクが高まるでしょう。アプリケーションセキュリティを実施することで、このようなリスクを軽減し、アプリケーションを安全に利用して業務が遂行できます。
自社開発のアプリケーションを使用する場合は事前にセキュリティ診断を実施し、一定のセキュリティレベルが維持できるかどうかをチェックしましょう。他社が開発した既存のアプリケーションを導入する場合、セキュリティレベルは開発会社およびサービス提供会社に依存しています。そのため、自社のセキュリティポリシーを満たしているかどうかを、事前に必ず確認しましょう。
WEBブラウザのセキュリティの強化
WEBブラウザを使用中にサイバー攻撃に遭うことも少なくないため、WEBブラウザのセキュリティの強化も重要です。まずは、WEBブラウザを常に最新の状態にアップデートしておきましょう。マルウェアなどのサイバー攻撃は、WEBブラウザの脆弱性を狙って侵入します。WEBブラウザを常に最新の状態にアップデートしておけば脆弱性に対処できるため、サイバー攻撃に遭うリスクが軽減されるでしょう。
また、WEBブラウザだけでなく、ツールバーやアドインのアップデートも忘れてはいけません。過去には、ツールバーそのものがスパイウェアの動きをするサイバー攻撃も発生したため、ツールバーやアドインの必要性が低い場合はインストールしないようにしましょう。
このほか、WEBブラウザに搭載されている「セーフブラウジング機能」が有効になっているかどうかもチェックしてください。セーフブラウジング機能とは、安全でないWEBサイトにアクセスした場合、警告が表示される機能です。多くのWEBブラウザに搭載されていますが、無効になっている場合もあるため確認が必要です。
社員間でパソコンを共有している場合は、閲覧履歴やキャッシュの削除や自動入力の無効化を忘れないようにしましょう。
従業員セキュリティリテラシー向上
従業員にセキュリティ教育を行い、セキュリティリテラシーの向上に努めることも重要です。従業員一人ひとりの意識が高まれば、自然と企業のサイバー攻撃に対する防御力も向上します。どのようなサイバー攻撃のリスクがあるのか、またサイバー攻撃に遭わないために、一人ひとりが心がけるべきことは何かを共有しておきましょう。
同時に、従業員のセキュリティインシデントの報告の重要性についても言及します。迅速なインシデント報告は、サイバー攻撃の早期発見・対策につながります。インシデントの報告フローを明確にし、定期的にシミュレーションやトレーニングを行うことで、スムーズなインシデント報告が可能になる環境が整います。
サイバーセキュリティに関する知識やスキルを有する人材を育成するために、情報セキュリティに関する資格取得を支援するのもひとつの方法です。資格試験に合格することで従業員はスキルアップにつながるだけでなく、企業は情報セキュリティ確保に貢献できる人材を育成できます。
まとめ
サイバー攻撃の被害に遭うと、経済的に多大な損失を被るだけでなく、社会的信頼も失ってしまいます。しかし近年サイバー攻撃の手口は巧妙化しており、被害を防ぐにはそれ相応の知識とスキルが必要です。
卑劣なサイバー攻撃から企業を守るためには、まずサイバーセキュリティとは何かをしっかり理解したうえで、有効な対策を講じることが重要です。また、従業員のセキュリティ教育を徹底することも大切なポイントです。
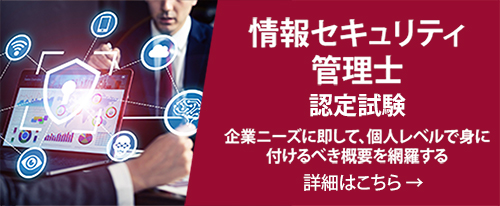
リスクマネジメントを学ぶ情報セキュリティ管理士