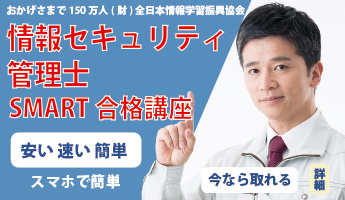生成AIは情報漏洩のリスクがある?知っておきたい対策と予防法
2025.4.10
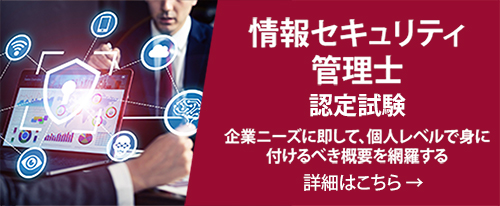
リスクマネジメントを学ぶ情報セキュリティ管理士
生成AIは情報漏洩のリスクがある?知っておきたい対策と予防法
生成AIを業務に活用する際の懸念事項が、情報漏洩のリスクです。この記事では、生成AIによる情報漏洩が発生する理由を紹介するとともに、情報漏洩を防止する対策や情報漏洩した際の対処法について解説します。生成AIを利用して業務効率化を目指したいという企業は必読の内容ですので、ぜひ最後まで読んで今後の参考にしてください。
▶まとめ
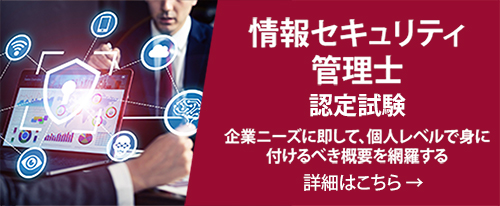
リスクマネジメントを学ぶ情報セキュリティ管理士
生成AIで情報漏洩が発生する可能性はある?

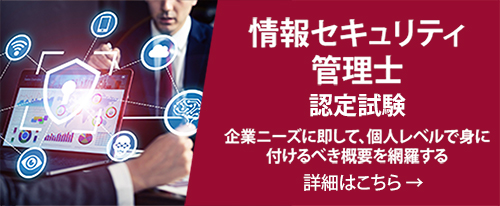
リスクマネジメントを学ぶ情報セキュリティ管理士
生成AIを使用すると、個人情報や機密情報が漏洩する可能性はゼロではありません。ChatGPTを開発・運営しているOpenAIは、個人情報保護のためにセキュリティの強化やデータの暗号化など、さまざまな対策を実施していると公表しています。
しかし、これまでに複数の個人情報漏洩や情報の流出が報告されています。大切な情報が外部に漏れないように、生成AIを使用する場合は高いセキュリティ意識を持つことが重要です。
生成AIで情報漏洩が発生する理由
生成AIで情報漏洩が発生する主な理由として、「AIの学習機能」「技術的なバグ」「セキュリティの問題」の3つの要因が挙げられます。それぞれについて詳しく解説します。
学習機能によって回答が第三者へと活用されるため
生成AIの学習機能により、以前入力した情報が第三者の回答へ活用されることで情報が漏洩する可能性があります。生成AIはユーザーの入力内容を学習し、参考にすることで回答しています。そのため、機密情報を生成AIに入力してしまうと、その情報が第三者への回答に流用される恐れがあるのです。
また、入力した内容は生成AIのデータに保存されます。たとえそれが活用されなくても、社外秘の情報が外部に保存されている状態がすでに情報漏洩である、と考える企業も少なくありません。
技術的なバグによるもの
生成AIの技術的なバグにより、情報が流出してしまうパターンもあります。たとえば、生成AIの回答にほかのユーザーの入力内容が反映されたり、本来ならアクセス不可のデータにアクセスできてしまったりするバグが発生する可能性が考えられます。
生成AIはプログラムやアルゴリズムが非常に難しいため、バグを完全に防ぐことは容易ではありません。そのため、常にバグ発生のリスクを考えながら生成AIを使うことが重要です。
セキュリティ対策が不十分なため
多くのAIは、クラウドサービスとして提供されています。そのため、生成AIのサービスを提供する側のセキュリティ対策が不十分な場合、サイバー攻撃によって情報が漏洩する恐れがあるでしょう。
実際に過去には、クラウドサービスが攻撃されて大量の個人情報が流出する事件が複数発生しています。生成AIもそのほかのクラウドサービスと同じくらいサイバー攻撃のリスクにさらされている、と考えておきましょう。
生成AIの情報漏洩でどのようなリスクがある?
生成AIで情報漏洩が起こると、ただ単に企業の情報が外部に知られるだけでなく、それに伴うさまざまなリスクが発生します。いずれのリスクも、企業に多大な損失や悪影響を及ぼしかねません。ここからは、情報漏洩でいったいどのようなリスクがあるのかを解説します。
社会的な信頼の損失
生成AIで情報漏洩が起こり、顧客情報や企業秘密が外部に流出すると、企業は社会的信用を失います。第三者からは「情報セキュリティへの意識が低い会社」というレッテルを張られ、新規開拓や契約継続が難しくなるでしょう。
近年はSNSが普及しているため、悪い評判はあっという間に世間に広まります。また、信頼回復には長い時間がかかるでしょう。その間、企業の経営に大きなダメージが生じる可能性も考えられます。
顧客との関係悪化
情報漏洩が原因で、顧客との関係が悪化してしまう恐れもあるでしょう。特に、重要な情報が流出し顧客に被害を及ぼした場合、損害賠償請求される恐れもあります。いくら長年かけて信頼関係を構築したとしても、崩れるのはあっという間です。一度失った信頼を取り戻すのは容易ではなく、最悪の場合、顧客との取引が終了してしまう可能性もあります。
生成AIによる情報漏洩を防ぐ方法
生成AIを使用する場合は情報漏洩のリスクを考え、事前に対策を講じる必要があります。ここからは、生成AIの情報漏洩を防ぐために有効な方法をいくつかピックアップして紹介しますので、参考にしてください。
生成AI利用時のルールを設定する
生成AIを利用するにあたり守るべきルールを策定し、従業員に周知しておきましょう。ルールを明確化することで、従業員も情報漏洩のリスクやセキュリティの重要性を理解でき、適切な取り扱いができるようになります。
ルールを広報するだけでなく、継続的な教育も重要です。生成AI利用時のガイドラインについて定期的に勉強会を開けば、従業員のセキュリティに対する意識がより一層高まるでしょう。
生成AIが作成した回答を担当者がチェックする
生成AIの回答に情報漏洩のリスクがないかどうか、人による精査を行いましょう。情報セキュリティに精通した専門の担当者が、生成AIの回答をチェックし、情報漏洩や著作権侵害のリスクがないかどうかを確認します。
生成AIが作成した文章をそのまま使うのではなく、人の目による確認を入れることで情報漏洩のリスクは大きく削減します。また、情報漏洩のチェックと同時に内容の事実確認も行えば、より精度の高いコンテンツが作成できます。
セキュリティサービスを活用する
情報漏洩対策のセキュリティサービスを活用するのもひとつの方法です。セキュリティサービスを活用してユーザーアカウントを管理したり生成AIの利用状況を把握したりすれば、情報漏洩リスクを軽減できます。また、人的ミスによる情報漏洩の防止対策やサイバー攻撃対策にも有効です。
このようにセキュリティサービスを利用すれば、生成AIによる情報漏洩だけでなく、あらゆるリスクに対応できます。その結果、管理担当者の負担が削減し、業務の効率化も図れるでしょう。
生成AIが入力内容を学習しない設定・プランにする
ChatGPTなど一部の生成AIでは、ユーザーのやり取りの履歴が残らない設定が可能です。履歴を残さない設定にしておけば、誤って機密情報を入力しても、それが第三者の回答に流用される恐れはありません。
ただし、OpenAI社では不正利用に備えて、履歴が残らない設定にしても30日間はデータが保存されています。また、履歴が残らないようにすることで、過去の入力内容とその回答が閲覧できなくなることも覚えておきましょう。
セキュリティの高い生成AIを活用する
セキュリティが高い生成AIを利用することも重要です。セキュリティの高いAIの特徴は以下のとおりです。
- ・データ暗号化の技術を採用している
- ・アクセス管理が厳格である
- ・定期的なセキュリティ更新およびパッチを採用している
これらが実装された生成AIを選択すれば、情報漏洩のリスクはかなり軽減されるでしょう。一般的に無料の生成AIはセキュリティツールが制限されているため、有料の生成AIを使うようにしましょう。
機密情報は入力しない
機密情報は絶対に入力しないことで、生成AIによる情報漏洩を防止できます。機密情報だけでなく、顧客の個人情報や業務上で取得した情報、社外秘の情報なども入力しないようにしましょう。
先ほどからお伝えしているとおり、生成AIはユーザーとのやりとりから学習し、入力したプロンプトを参考にして回答しています。機密情報を入力すれば、第三者への情報流出に直結するという意識を常に持っておきましょう。
従業員の生成AI使用リテラシーを向上する
従業員に情報セキュリティ教育の機会を設け、生成AI使用時のリテラシー向上に努めることも大切です。従業員教育では、過去に起きた生成AIによる情報流出事例や、生成AIによる情報漏洩が発生したときのペナルティを共有し、情報漏洩の脅威について周知しましょう。
また、情報漏洩に対する具体的な対策を徹底しておけば、社内の情報セキュリティ向上にも役立つでしょう。情報セキュリティ教育によって従業員が適切に生成AIを利用できるようになれば、業務のさらなる効率化が図れます。
生成AIによる情報漏洩が起きたときの対処法

どれだけ情報漏洩の対策を徹底しても、リスクをゼロにすることはできません。そのため、情報漏洩が起きたときに、どのような対処をするべきかを考えておくことも重要です。ここでは、生成AIによる情報漏洩が起きた際の対処法について順を追って解説します。
速やかに事実関係を確認する
まずは、速やかに事実関係を確認します。どのような内容の情報が漏洩しているのか、またどこまで情報が広がっているのか、5W1Hの観点からひとつずつ事実をチェックしましょう。さらに、事実の裏付けをとることも大切です。
対応が遅れてしまうと、解決に時間がかかる可能性があります。事実関係の確認は、冷静かつスピーディーに行いましょう。
対応を検討し、状況を発信する
事実関係が確認できたら、被害拡大を阻止するための対策を検討します。それと同時に、情報漏洩が起きた事実や情報漏洩の内容について、顧客や監督官庁、警察などに報告しなければなりません。また、顧客の信用を保持するために、プレスリリースなどを活用して対応情報を発信することも大切です。
個人情報保護法では、個人に被害をもたらす可能性がある情報が流出した場合、個人への通知および個人情報保護委員会へ報告することが義務付けられています。報告が遅れたり、事実を隠蔽したりすると、社会的信頼回復が難しくなるだけでなく、罰則の対象となる可能性もあるので注意してください。
削除請求を行う
漏洩した情報がインターネット上で公開されている場合、速やかに削除請求を行いましょう。サイトポリシーを踏まえて削除理由を明確にすれば、情報が迅速に削除される可能性が高くなります。
相手が削除要請に応じない場合は、削除の仮処分の申し立ても可能です。また場合によっては、漏洩された情報の投稿者の特定や損害賠償請求もできるため、弁護士に相談するのもおすすめです。
関係者への懲戒処分を検討する
機密情報の漏洩を引き起こした従業員に対する処分も検討しなければなりません。情報漏洩に対する罰則ルールが明確化されている場合は、その規則に準じて処分します。ただし、従業員の行為の性質や態様を把握し、適切な処分を行いましょう。重すぎる懲戒処分を下してしまうと、労働契約法第15条により処罰が無効となる可能性があります。
罰則ルールが明確化されていない場合は、過去の裁判例や処罰の事例などを参考にするとよいでしょう。
再発防止策を考える
生成AIによる情報漏洩が再度起きないように、再発防止策を考えます。前述したとおり、セキュリティーソフトを導入したり、生成AI利用時のルールを明確化したりするなどして、二度と同じ事例が起きないような対策を講じなければ、社会的信頼の回復は望めません。
従業員のリテラシー向上の一環として、情報セキュリティ管理の資格取得を推進するのもひとつの方法です。情報セキュリティ管理のプロが企業に在籍するようになれば、企業のセキュリティ意識の高さを顧客にアピールできますし、もしもの際も迅速かつ的確に対応できるでしょう。
情報セキュリティ管理の資格試験には、「情報セキュリティ管理士認定試験」「個人情報保護士認定試験」などがあります。ぜひ自社にあった資格の取得を検討してみてください。
まとめ
生成AIは、適切に使用すれば業務の大幅な効率化が図れます。しかし、情報漏洩のリスクが潜んでいることを忘れてはなりません。生成AIを使用する際は機密情報を入力しない、セキュリティの高い生成AIを使用するなど、情報漏洩のリスクが軽減できるような対策を実施しましょう。
また、従業員の情報セキュリティに対するリテラシーを向上することも大切です。定期的に生成AI利用時の勉強会を行うことや、生成AI利用時のルールを明確にすることを心がけましょう。さらに、情報セキュリティ管理士など情報セキュリティに関する資格取得を推進すれば、従業員の意識も向上するはずです。
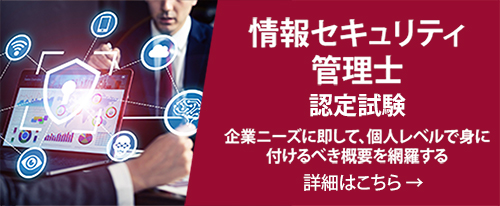
リスクマネジメントを学ぶ情報セキュリティ管理士